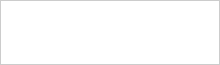こんにちは。学び舎高屋の寺田です。
勉強をしているといろいろな語呂合わせに出会いますね。
私が子どもの頃(約40年前!)は、710年平城京は、「なっとう(納豆)食べて平城京」と覚えたものですが、最近では「なんと(710)見事な平城京」と覚えるといった具合に語呂合わせにもトレンドがあるようです。実際「645年大化の改新」を「むしごめ(蒸し米)炊いて大化の改新」なんて言った日には、「そもそも蒸し米とは…」というところから説明しなくてはいけなくなって大変です。
さて、先日、中学生の数学の勉強で球の表面積を求める公式がでてきました。
「S=4πrの2乗」というものですが、これに「しんぱい(心配)あーるの2乗」という語呂合わせがあることを私は知りませんでしたが、なかなかの秀作で感心しました。体積の方は、どうやらないようなのですが、ひょっとすると存在するのでしょうか。また、きょり・はやさ・じかんの求め方を「き・は・じ」とか「は・じ・き」と言うのは知ってましたが、「『き』の下の『は』げおや『じ』」で覚えるという生徒がいました。これは、「きの下」までは良いのですが、最後に無理があるのと品がないのとで感心できません。
以前、ある高校生が「swallow=丸呑みする」という単語を覚えるのに「先生、いいのを思いついたよ!swallow、『ツバメを丸呑み』ってどう?」と言ってきたことがありました。彼には、その時、じっくりと「そもそも語呂合わせとは…」から教えてあげたのを思い出します。語呂合わせもなかなか難しいですね。